相続について

相続とは、人の死亡によって、被相続人(亡くなられた方)の財産上の法律関係(権利義務)をすべて、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
つまり、相続とは、被相続人(亡くなられた方)に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。
被相続人(亡くなられた方)から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産、または、遺産と呼び、引継ぐ相続財産には、土地、建物、現金、銀行の預貯金のみならず、知人へ貸付金や、売掛金などの債権も相続の対象になります。
また、このようなプラスの相続財産だけではなく、借金や損害賠償債務といったマイナスの相続財産も相続されます。相続で忘れてはならないこと、被相続人(亡くなられた方)から相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて含まれるということなのです。
但し、次のものは例外で、相続により承継しないものとなります。
- 被相続人(亡くなられた方)の一身に専属したものは、相続で承継されません。
- 例えば、扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など、被相続人(亡くなられた方)の一身に専属していたものは、相続として承継されないものとされています。
- 位牌、墳墓などの祭祀財産も、相続で承継されません。
- 例えば、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、但し、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として、所有しているものは相続税がかかります。
- 生命保険金、死亡退職金、遺族年金など、契約や法律に基づいて支払われるものも相続で承継されません。
- ※遺 贈
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいい、贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます。
- 例えば、
- 自分達の親にはほとんど財産は無いので、遺産相続の心配はありません。
- いつも、親からは「家には現金も預金も無いからね」と聞いている。
- 私達の兄妹は仲がいいので、もめる事はないと思う。
- 親の遺産相続なんて、お金持ちの話なので、自分には関係ないと考えている。
このように、考えている方が多いと思いますが、先程紹介したように、相続は、現金や銀行預金のようなプラスの財産と、反対のマイナス財産(負の遺産)も対象になるため、注意する必要があります。
- 具体的な相続税のあらまし
- 相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
- 相続と遺贈
- 相続は原則として、死亡によって開始し、そして、相続人は相続開始の時から、被相続人(亡くなられた方)の財産に関する一切の権利義務を承継することになり、但し、扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など、被相続人の一身に専属していたものは、承継されません。
- 遺贈とは被相続人(亡くなられた方)の遺言によって、その財産を移転することをいい、注意したいのは、贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といい)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます。
相続時精算課税に係る贈与について
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。
贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告時に贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があり、この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。
- 相続人について
- 民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めて、但し、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
- 被相続人(亡くなられた方)の子。子が被相続人(亡くなられた方)の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が、相続人となります。
- 被相続人(亡くなられた方)に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人(亡くなられた方)の父母が相続人。父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となります。
- 被相続人(亡くなられた方)に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹が相続人。兄弟姉妹が、被相続人(亡くなられた方)の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。
相続の対象である相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて含まれるということ。
例えば、具体的な例とすると、
- 「お亡くなりになった方が、金融機関からの借入金があった」
- 「妻や家族に内緒で、商店を経営している同級生の連帯保証人になっていた」
- 1.や2.の場合において、相続が開始した場合、
相続人は以下の中でいずれかを選択できます。
相続人が、2の相続放棄または、3の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりませんので、ご注意する必要があります。
以下では、2の相続放棄についてご紹介します。
- 申述人
-
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
- 申述期間
-
申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければならないと定められています。この手続きには3ヶ月という期限が定められているので、家庭裁判所に
『相続放棄申述書』
を提出する必要があるのですが、また、この3ヶ月という期間を計算する基準日は、
『自分が相続人となった事を知った日』
を基準とし、故人が亡くなった日ではないのでご注意ください。
- 申述先
-
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
相続に関係する、被相続人(亡くなった方)と、
相続人(亡くなった方の財産的地位を受け継ぐ人が相続人)
相続は、被相続人(亡くなった方)の財産の全部または一部を、子や妻など、被相続人(亡くなられた方)と一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことです。
事実婚のパートナーは相続人ではないので原則的に財産を受け継ぐことはできませんが、但し、財産を事実婚のパートナーに引き継がせる旨の遺言があれば相続人と同じように、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐことができます。
相続によって受け継がれる財産のことを相続財産、または、遺産と呼び土地、建物、現金などの現物、貸金や売掛金などの債権も相続財産ですが、借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続人に相続されますので、相続人になられた方は、詳細を確認する必要があります。
具体的には、連帯保証人などの保証債務も例外ではなく、被相続人(亡くなった人)が誰かの連帯保証人になっていれば、原則として相続人がその地位を受け継ぎ、つまり、他人の借金の返済義務を負ってしまうのが相続です。
相続というのは、人の死亡によって何の手続も意思表示もなく当然に生じるもので、したがって、相続の放棄や限定承認の手続きをしない限り、被相続人(亡くなられた方)の全財産 、マイナスの借金等の債務もすべてを一切引き継ぐことになるのです。
法定相続と遺言による相続
- 相続の2種類
- 法律の規定による相続→→→法定相続
- 被相続人(亡くなられた方)の意思による相続→→→遺言による相続
民法は当事者の意思を尊重することを第一に、いろいろな制度を定めて、相続に関しても同様で、被相続人(亡くなった方)の意思を最優先で実現するように、遺言による相続を法定相続に優先させています。
遺言書があれば基本的にその内容通り相続が行われることを認め、遺言書がない場合には法定相続によって相続が行われます。
- 相続は、死亡によって開始
-
民法の規定 相続は、死亡によって開始する。
死亡には、法律上死亡とみなされる失踪宣告や認定死亡を含まれ、
- 相続の開始には、死亡以外の原因はありません。
- 相続が開始する時期は、その人が死亡した瞬間です。
昔の民法には生きていても相続が開始することがあり、それは、隠居した場合で、つまり 、現在は、そのような生前相続はありえないと言うことを宣言 しているのです。 次は、死亡した瞬間に生きている人に財産権が瞬時に移動することを意味しており、従って、死亡の瞬間に生きている人だけが相続を受けられて、
例えば、父親が死亡する1秒でも前に子が死亡したらその子には相続する権利はなく、父親とその子が同時に死亡した場合も相続開始の瞬間に子はいないのですから同様で、2011年(平成23年)3月11日(金)に発生した東日本大震災のような状態で、どちらが先に死亡したのかはっきりしない場合、そうなると、子供が先に死亡した場合と後の場合では相続できる人が大きく変わるので誰が父親の財産を相続するのか決められません。
そのような場合は民法によって、2人は同時に死亡したものと推定され、そうすると、誰が財産を相続するか、はっきりと決められるわけです。
税理士のご紹介、まずは、確認してみましょう!
ここから以下は全国ネットワークで税理士を紹介している会社です。
ご提携いただく税理士は、すべて事前に税理士の面談を行い、厳しい審査に合格した方のみをご紹介しています。
税理士・会計事務所の報酬、相続手続きの金額、月次監査の金額が適正価格かどうかなど、経験と実績が豊富なプロが第三者目線で、的確なアドバイスをしてくてます。
この機会に『税理士ドットコム』『税理士紹介エージェント』へメールで依頼して、相続の手続き、会社の設立や今の税理士の見直し、ご自身がいいと思う最適な選択をしましょう。
税理士ドットコムへのお問合せをご希望の方はこちらで。
相続での税理士選びなら税理士ドットコム
広告|クリックして、税理士ドットコムのホームへ


こんな結果にならないために、
ケース1:申告後の請求金額が高額に・・。例えば、付き合いのある経営者、銀行から紹介された税理士に相続税申告について依頼したところ、申告後に届いた請求書には非常に高額な金額が記載されていた。
事前に金額を確認していなかったが、まさか、そこまで報酬が高額になるとは思いもしなかった。
ケース2:故人を軽んじる発言に不信感・・。友達に紹介された税理士に相続税申告の相談をしたところ、わかりやすい説明をしてくれはするものの、亡くなった故人を軽んじる発言が端々で見受けられどうしても信用できなかった。
こんなケースにならないように、事前に準備して確認しましょう。
相続での税理士選びなら税理士ドットコム 、お気軽にお問合せ下さい。
、お気軽にお問合せ下さい。
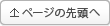
ページの先頭へ
![]() 、お気軽にお問合せ下さい。
、お気軽にお問合せ下さい。
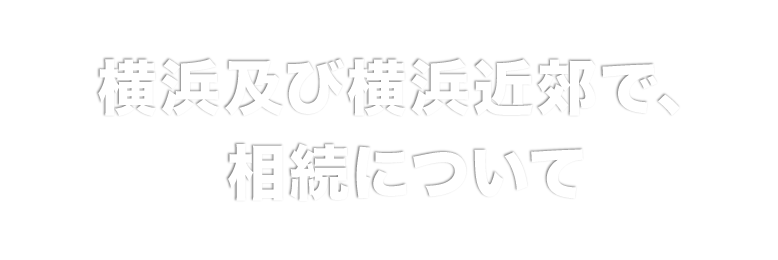

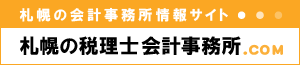




















(注) 配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。